下痢して食欲も落ちてピンチ状態だったニシヘルマンリクガメのベビー黄(きい)ちゃん。
看病の甲斐あって、体重が動物病院へ行ったときの17gから20gへと+3gアップしました~
(ちなみに甲長は4.3㎝です)
我が家へ来てからの経緯を忘備録として記録しておきます。
6月15日、黄ちゃん到着。このとき体重は19g。
↓
6月20日、下痢が始まり、食欲不振で餌を食べず。
↓
6月22日、獣医さんへ。体重17g。栄養剤の注射をしてもらう。
↓
6月26日、下痢が減り始める。食欲もかなり回復。
↓
6月27日、夕食後、体重が20gの大台に乗る。
獣医さんのお話だと、この甲長なら30gあって当たり前。少なくとも25gはあって欲しいところだそうで、20gではまだまだ安心できないけれど体重が増えてきているのは喜ばしいことです
減っていくようなら命の危機で、入院することもありえたんで。
獣医さんから帰ってきて、指示に従い飼育環境を改善した点は以下のとおりです。
1.飼育温度(ケージ内の温度)に高低差を付ける。
ベビーの飼育は30℃キープが良いとネットであちこちに書かれていたからそうしていたら「最低温度が高すぎる」んだそうです。最低部分は25℃が望ましいそうです。
でもリビングに黄ちゃんケージはあるから25℃まで下げちゃうと人間が寒いんで、エアコンを27℃に設定して室温は26℃~27℃をキープするようにしました。
(ホットスポット部分は30~35℃くらいになるよう以前から設定してます)
この飼育温度については、地中海リクガメのバイブルと言われる「TORTOISE LAND リクガメ飼育百科―完全飼育マニュアル」を調べてみると、確かに「常に28℃程度の温度を保っているとすると、この温度を好む寄生虫(原虫類)を増やす原因にもなります」と書かれています
そういうことだったのか~と納得。
もっと早く読んでおけばよかった。絶版の本だからオークションで手に入れたばかりで、まだそこまで読み進んでいなかったんですよね
2.昼前後の高温時を避けて、外に出して日光浴をさせる。
ベランダでの日光浴はそれまでさせてはいましたが、一日10分程度でした。
獣医さんの指示では昼の暑い時間帯を除き、朝と夕に日光浴をさせてやってということで、朝は10時くらいまで2時間くらい日光浴させるよう改善しました。
夕方は仕事で不在のためなかなかできないけれど、休日は夕方も出してやるようにしています。
曇っていたり日陰でも、室内や紫外線灯より断然外の方が紫外線は強いから、毎日かかさず出してやってます。

 百円ショップで買ってきたバーベキュー網を結束バンドでつないで、鳥にさらわれないよう蓋もしています。プランターに上ってお食事もできるよう、段ボール紙で坂を作ってみましたが、まだ黄ちゃんは一度も登ってくれません
百円ショップで買ってきたバーベキュー網を結束バンドでつないで、鳥にさらわれないよう蓋もしています。プランターに上ってお食事もできるよう、段ボール紙で坂を作ってみましたが、まだ黄ちゃんは一度も登ってくれません
同じところで眠ってばかりいて、せっかくのお庭なのに遊んでくれなくてつまんないよ~
3.朝夕、温浴をさせる。
それまでも朝だけ温浴させていましたが、脱水症状をとにかく改善しないといけないということで、夕方も温浴させることにしました。可能なときは昼も入れてます。
温浴中に顔をつけて自ら水を飲んで水分補給にもなるし、体が温まって活動的になるからその後の給餌で食欲が出るメリットもあります。
温浴は一回15分くらい入れてやるようにしています。
体が小さいから水量もごくわずかなので、水温がすぐ冷めてしまうため、下からパネルヒーターのスーパー1で温め、上からはバスキングスポットランプで温めています。
それでもぬるくなったときは新しくお湯を入れた洗面器と交換してやってます。
4.水分の多い餌を与える。
キュウリやレタスなど、水分の多い野菜を与えて脱水症状から脱することが先決だそうです。
でも黄ちゃん、あんまり野菜は好きじゃないみたい。キュウリ、トマト、多肉植物のセダムや子宝草を初めて与えた日は結構食べたんですが、翌日からは食べなくなりました。
コンスタントに食べてくれたのはタンポポの葉やシロツメグサなど野草類です。
今朝は初めて、レンジでチンした人参とカボチャを与えてみました。最初は無視されたけど、野草を食べさせた後でリベンジしてみたら食べてくれました
黄ちゃんて、食べ物の臭いを最初に嗅いで、食べるかどうか決めてるみたい。
好きな餌とのきはくんくんした後すぐパクつきはじめますが、そうでもないときはくんくんにおった後プイッと違う方を向いてしまいます
この一週間は「とにかく食べさせて太らせなくちゃ」と、付きっきりで給餌してます。プイッてなったら、別の餌を口元に持っていってやる...って感じで。すごい過保護してます
26日夕方からは、注文していたレプラーゼとレプチゾルが届いたので使っています。これらは獣医さんの指示ではなく自己判断で。
レプチゾルはビタミンの栄養剤で、温浴の水に1滴入れるようにしました。
でも、昨日から首とシッポの脱皮があって皮が一部めくれていて、普通の脱皮なら成長の証だろうから良いのですが、ビタミン過剰摂取で脱皮みたく皮がめくれることがあるらしいので、怖くなって使用を一時中断しました。
レプラーゼは爬虫類用の生きた腸内細菌で腸内の病原菌の増殖を抑えてくれる効果があるそうで、原虫わんさかになってた黄ちゃんの腸内善玉菌も数が減ってるんじゃないかと考えて、善玉菌を増やすことで原虫を抑えてくれることを期待して餌に添加して与えるようにしています。
レプラーゼは与えすぎによる弊害がないそうで、安心して使えるみたい。
ただ、レプラーゼを付けると、好きな野草も食いが悪くなってる気がします。臭いや味が好きじゃないのかも
こんなふうに、いろいろ飼育方法を改善した結果なのか、自然治癒力のせいなのか分かりませんが、順調に体重が増えはじめている状態になりました
今日の夕方には0.1g単位ではかれる高精度スケールが届くので、より正確な状態を把握できそうです。
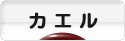
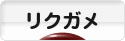
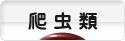
看病の甲斐あって、体重が動物病院へ行ったときの17gから20gへと+3gアップしました~

(ちなみに甲長は4.3㎝です)
我が家へ来てからの経緯を忘備録として記録しておきます。
6月15日、黄ちゃん到着。このとき体重は19g。
↓
6月20日、下痢が始まり、食欲不振で餌を食べず。
↓
6月22日、獣医さんへ。体重17g。栄養剤の注射をしてもらう。
↓
6月26日、下痢が減り始める。食欲もかなり回復。
↓
6月27日、夕食後、体重が20gの大台に乗る。
獣医さんのお話だと、この甲長なら30gあって当たり前。少なくとも25gはあって欲しいところだそうで、20gではまだまだ安心できないけれど体重が増えてきているのは喜ばしいことです

減っていくようなら命の危機で、入院することもありえたんで。
獣医さんから帰ってきて、指示に従い飼育環境を改善した点は以下のとおりです。
1.飼育温度(ケージ内の温度)に高低差を付ける。
ベビーの飼育は30℃キープが良いとネットであちこちに書かれていたからそうしていたら「最低温度が高すぎる」んだそうです。最低部分は25℃が望ましいそうです。
でもリビングに黄ちゃんケージはあるから25℃まで下げちゃうと人間が寒いんで、エアコンを27℃に設定して室温は26℃~27℃をキープするようにしました。
(ホットスポット部分は30~35℃くらいになるよう以前から設定してます)
この飼育温度については、地中海リクガメのバイブルと言われる「TORTOISE LAND リクガメ飼育百科―完全飼育マニュアル」を調べてみると、確かに「常に28℃程度の温度を保っているとすると、この温度を好む寄生虫(原虫類)を増やす原因にもなります」と書かれています

そういうことだったのか~と納得。
もっと早く読んでおけばよかった。絶版の本だからオークションで手に入れたばかりで、まだそこまで読み進んでいなかったんですよね

2.昼前後の高温時を避けて、外に出して日光浴をさせる。
ベランダでの日光浴はそれまでさせてはいましたが、一日10分程度でした。
獣医さんの指示では昼の暑い時間帯を除き、朝と夕に日光浴をさせてやってということで、朝は10時くらいまで2時間くらい日光浴させるよう改善しました。
夕方は仕事で不在のためなかなかできないけれど、休日は夕方も出してやるようにしています。
曇っていたり日陰でも、室内や紫外線灯より断然外の方が紫外線は強いから、毎日かかさず出してやってます。

 百円ショップで買ってきたバーベキュー網を結束バンドでつないで、鳥にさらわれないよう蓋もしています。プランターに上ってお食事もできるよう、段ボール紙で坂を作ってみましたが、まだ黄ちゃんは一度も登ってくれません
百円ショップで買ってきたバーベキュー網を結束バンドでつないで、鳥にさらわれないよう蓋もしています。プランターに上ってお食事もできるよう、段ボール紙で坂を作ってみましたが、まだ黄ちゃんは一度も登ってくれません
同じところで眠ってばかりいて、せっかくのお庭なのに遊んでくれなくてつまんないよ~

3.朝夕、温浴をさせる。
それまでも朝だけ温浴させていましたが、脱水症状をとにかく改善しないといけないということで、夕方も温浴させることにしました。可能なときは昼も入れてます。
温浴中に顔をつけて自ら水を飲んで水分補給にもなるし、体が温まって活動的になるからその後の給餌で食欲が出るメリットもあります。
温浴は一回15分くらい入れてやるようにしています。
体が小さいから水量もごくわずかなので、水温がすぐ冷めてしまうため、下からパネルヒーターのスーパー1で温め、上からはバスキングスポットランプで温めています。
それでもぬるくなったときは新しくお湯を入れた洗面器と交換してやってます。
4.水分の多い餌を与える。
キュウリやレタスなど、水分の多い野菜を与えて脱水症状から脱することが先決だそうです。
でも黄ちゃん、あんまり野菜は好きじゃないみたい。キュウリ、トマト、多肉植物のセダムや子宝草を初めて与えた日は結構食べたんですが、翌日からは食べなくなりました。
コンスタントに食べてくれたのはタンポポの葉やシロツメグサなど野草類です。
今朝は初めて、レンジでチンした人参とカボチャを与えてみました。最初は無視されたけど、野草を食べさせた後でリベンジしてみたら食べてくれました

黄ちゃんて、食べ物の臭いを最初に嗅いで、食べるかどうか決めてるみたい。
好きな餌とのきはくんくんした後すぐパクつきはじめますが、そうでもないときはくんくんにおった後プイッと違う方を向いてしまいます

この一週間は「とにかく食べさせて太らせなくちゃ」と、付きっきりで給餌してます。プイッてなったら、別の餌を口元に持っていってやる...って感じで。すごい過保護してます

26日夕方からは、注文していたレプラーゼとレプチゾルが届いたので使っています。これらは獣医さんの指示ではなく自己判断で。
レプチゾルはビタミンの栄養剤で、温浴の水に1滴入れるようにしました。
でも、昨日から首とシッポの脱皮があって皮が一部めくれていて、普通の脱皮なら成長の証だろうから良いのですが、ビタミン過剰摂取で脱皮みたく皮がめくれることがあるらしいので、怖くなって使用を一時中断しました。
レプラーゼは爬虫類用の生きた腸内細菌で腸内の病原菌の増殖を抑えてくれる効果があるそうで、原虫わんさかになってた黄ちゃんの腸内善玉菌も数が減ってるんじゃないかと考えて、善玉菌を増やすことで原虫を抑えてくれることを期待して餌に添加して与えるようにしています。
レプラーゼは与えすぎによる弊害がないそうで、安心して使えるみたい。
ただ、レプラーゼを付けると、好きな野草も食いが悪くなってる気がします。臭いや味が好きじゃないのかも

こんなふうに、いろいろ飼育方法を改善した結果なのか、自然治癒力のせいなのか分かりませんが、順調に体重が増えはじめている状態になりました

今日の夕方には0.1g単位ではかれる高精度スケールが届くので、より正確な状態を把握できそうです。














黄ちゃんの様子がとても気になっていましたが、
少し回復してきたようで、ほっとしています。(^_^)
段ボール紙は、接着剤とか人間には気がつきにくい、においとか
化学物質がついているかも・・・。(^_^;)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%B5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB
お忙しい所恐れ入ります。
3日前にヘルマンリクガメのベビーを迎えました。
ショップでは非常に活発で餌食いも良好でこの仔に決めお迎えしました。
帰宅後、ケージに入れ餌を置いたところ少し食べていて安心しておりました。
その日はシェルターの隅で寝ておりました。
次の日、起きてくる気配もなく寝ているようです。
朝にご飯を設置し寝ている所を起こしてご飯場に置くと暫くボーッとしてから少し食べてその後はまた眠りに・・・
3日目本日20日なんですが、前日と同様にずっと寝てる感じです。
お昼ご飯前に温浴をさせました。約15分程。持ち上げて体を拭いてる時に尿酸混じりのオシッコをぴゅーッとひっかけられました。
ケージに用意していた昼ごはんに温浴上がりのヘルマンさんを置くと少し食べていました。
その後は又寝てばかり・・・
ショップでの活発な姿はどこへやら。。。と言う感じで困っており、色々とサイトをさ巡っている時にこちらのサイトに巡り付きました。
お迎えにあたり、事前に色々とリサーチして万全の体制で迎えたつもりでしたが中々難しいですね。
ケロミンな日常さんも書かれている通りベビーの間はケージ温度高め30度推奨‼‼‼昼夜の温度差は2度位が良い!!!と多数で拝見し私もその設定温度でおりましたがやはりコレがまずい可能性があるんでしょうか?
黄ちゃんの時に病院の先生がおっしゃられてるように温度が低いところは25度くらい。最低部分は25℃が望ましい。室温は26℃~27℃をキープするくらいの温度の方がいいのか悩んでおります。
常に28℃程度の温度を保っているとすると、この温度を好む寄生虫(原虫類)を増やす原因にもなります。とあるようにお迎え後の新しい環境でのストレスで28℃~31℃どいう高い温度で原虫類が増えている可能性もありますよね。
飼育ケージはかめぢからケージを参考に自作しました。
左端にホットスポット35度位でサーモ管理。
メタハラ稼働でケージ内は日中30度前後。一番低い所で29度くらいです。
湿度は50~65%位になります。
ケロミンな日常さんのブログをみて夕方に急遽メタハラの稼働を取りやめ(ケージ温度が30度回避の為)スパイラル蛍光灯に変更。
暖突、セラミックヒーターのサーモ設定を26℃~27℃になる位に変更しました。
橙ちゃんお迎え後からのかめぢからケージでの温度設定はどのようにされていましたでしょうか?なんとか今いてるヘルマンさんを元気に過ごさせてやりたくて。。。
ご助言いただけると助かります。
ヘルマンさん、今頃になってコメントに気が付きました。
ご相談時にお役に立てなくてごめんなさい。
私も素人なので、その時気が付いていても「早めに獣医さんに相談して」くらいしか助言できなかったと思いますが。
星ちゃんお迎え当時のこと、もうあまりよく覚えていないです…。
でも同じくらいの大きさのベビーでお迎えした桜と杏子は、不安にさせられることもなく楽に育てられたので、個体差というか、購入時の健康状態によって、こんなに差があるもんなのだと実感した覚えがあります。
ヘルマンさんちのベビーちゃんは、その後、元気になられましたか?
元気になってますように…。